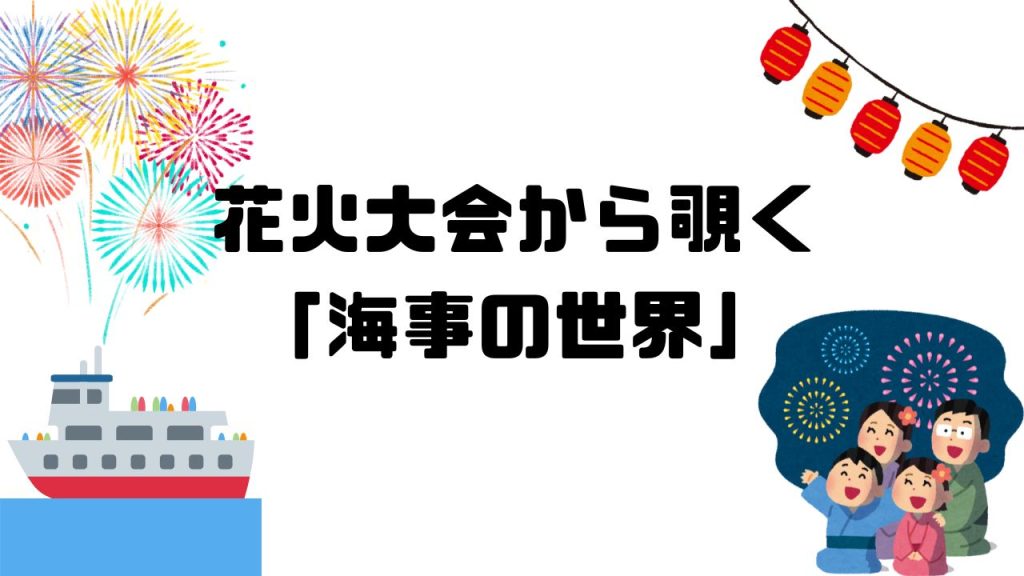
こんにちは。一瀬汽船株式会社です。
夏の夜空を彩る花火大会。家族や友人・恋人と見に行くという方も多いのではないでしょうか。
そんな夏の風物詩でもある花火大会で、先日残念なニュースがありましたね。
2025年8月4日に、みなとみらい地区で開かれた花火大会において、花火を打ち上げるための台船で火災が発生。
火は花火の火薬に引火したとみられ、台船では次々に花火が爆発。火は発生からおよそ15時間後に鎮火されました。
原因はまだ明らかになっておらず、横浜市観光協会は、今月10日に火災の現場近くで予定していた打ち上げ花火のイベントを急きょ中止にしました。
その他の地域においても開催予定が続く花火大会。安全第一で行われるを願っております。
本日は、花火大会から「海事の世界」を覗いていきたいと思います。
花火大会を開催するためには許可がいる?
花火大会を開催するためには、都道府県、消防署、警察など多くの関係各所からの許可がいりますが(詳しくは、こちら(公益社団法人日本煙火協会))、「港内」で花火を打ち揚げる場合「港長の許可」が必要になる可能性が高いため、確認が必要です。
参考にしたいのが、港内における船舶交通の安全及び港内の整とんを図ることを目的とした「港則法」です。
港則法第32条 特定港内において端艇競争その他の行事をしようとする者は、予め港長の許可を受けなければならない。
まず、港則法についての余談ですが・・・。
港則法が適用される港「適用港」は、同法第2条に定められており、全国で502港あります。
この502港の内、喫水の深い船舶が出入できる港又は外国船舶が常時出入する港を「特定港」として定めおり、全国で86港あります。
特定港には「港長」が置かれており港則法の事務を行っています。一方、特定港以外の適用港の事務は管轄する「海上保安部長(又は海上保安署長)」が行うこととなっています。
さて、港則法第32条に話を戻しまして。
特定港内で行われる行事は、一定の水域を占有し又は通常の船舶交通流を乱すこととなり、船舶交通に影響を及ぼすおそれがあるため、港則法に基づく「港長の許可」が必要となります。
行事とは、端艇競争、花火大会、祭礼、パレード、海上訓練、潜水訓練、操船訓練、遠泳大会、SUPレース、海上デモ等を指します。花火大会は、危険物荷役を伴うため、計画段階から十分な事前説明が必要な行事といえます。
許可に伴う申請書類は、実施計画書のみならず、安全管理体制について、緊急時の連絡体制について、周知先について、警戒・救助船艇の配備について、安全対策について等など、多岐に渡ります。(主催者に感謝です・・・。)
特定港以外の適用港における行事については、海上保安部長の許可を要しませんが、同行事に伴い実施海域に「ブイを設置する」「クレーン台船で構造物を設置する」などの付帯作業が発生する場合は、原則として許可申請が必要となります。
なお、許可申請に該当しない場合についても、事故防止、船舶交通の安全確保の見地から、主催者に対し「お知らせ」として情報提供を求めることがあり、必要な場合は、海上保安庁が提供している「海の安全情報」及び「水路通報」に掲載されています。そのため、許可を要しない作業であっても、航行するエリアが限られている港内ということを考えると、事前に管轄する海上保安署や港湾管理者と協議・情報共有をすることが望ましいです。
ちなみに、火災があった現場の横浜港は特定港であるため、予め港長の許可を受けて開催されたと思われます。
台船って船じゃない?
台船とは、主に海上工事や港湾工事で使用される、平底で箱型の形状で、業界内では「はしけ」や「バージ」と呼ばれます。資材や重機の運搬、仮置き場として利用されることが多いですが、海上花火大会の発射台としても利用されています。自力航行能力を持たないため、タグボートに曳航されて移動するのが特徴です。
台船と名前に船がついていますが・・・実は船舶法上、船舶には該当しません。なぜなら、自力航行能力を持たないからです。船舶法施行細則を見てみると、「推進器を有していない浚渫船は船舶とはみなさない」とあります。
船舶法施行細則第2条 浚渫船ハ推進器ヲ有セサレハ之ヲ船舶ト看做サス
台船は何なのか?というと「建設機械」に該当します。
船舶法上の船舶であれば20トン以上であれば登記・登録、20トン未満の小型船舶でも登録が必要ですが、台船は対象外となります。
しかし注意が必要なのは、台船は船舶法の登録は対象上は外ですが、使用方法や積載物によっては「船舶安全法」の適用を受ける場合があります。
船舶安全法2条2項
船舶ハ左ニ掲グル事項ニ付国土交通省令(漁船ノミニ関スルモノニ付テハ国土交通省令・農林水産省令)ノ定ムル所ニ依リ施設スルコトヲ要ス
(省略)
十 危険物其ノ他ノ特殊貨物ノ積附設備
(適用除外)船舶安全法施行規則第2条2項
三 推進機関及び帆装を有しない船舶(次に掲げるものを除く。)
イ 国際航海に従事するもの
ハ 平水区域を超えて航行するもののうち、推進機関を有する他の船舶に押されて航行の用に供するもの(沿海区域を航行区域とする推進機関を有する船舶と結合し一体となつて航行する船舶であつて平水区域及び平水区域から最強速力で四時間以内に往復できる区域のみを航行するもの並びに管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認めるものを除く。)
ニ 危険物ばら積船(危険物船舶運送及び貯蔵規則第二百五十七条の二の液体油脂ばら積船であつて平水区域のみを航行するものを除く。)
製造した花火を海上輸送して打ち上げ地点まで航行する場合、船舶安全法施行規則第2条2項3号のイ・ハが該当する可能性があります。また、火薬の積載量によっては、危険物に該当し、平水区域を越えて航行する場合、船舶安全法施行規則第2条2項3号のニが該当する可能性があります。
船舶安全法が該当する場合は、臨時航行検査の受検、危険物の積み付け検査、収納検査が必要になるケースがあります。
(危険物関係の法令は、「危険物船舶運送及び貯蔵規則」)
もし海上で火災が起こったら、消火は誰がする?
船舶火災の消火活動について、港湾所在市町村の消防機関と海上保安官署間で業務協定が締結されていることをご存じでしょうか。
船舶火災の消火活動については、港湾所在市町村の消防機関と海上保安官署間で業務協定が締結されており、「ふ頭または岸壁にけい留された船舶および上架または入渠中の船舶」「河川湖沼における船舶」の消火活動は主として消防機関が担任し、上記以外の船舶火災については現地の実情に応じて海上保安官署との協議により定めることとなっています。
また、船舶の火災の原因並びに火災及び消火により受けた損害の調査も、海上保安官署と消防機関が協議して、これを行なうことになっています。
火災が起きたみなとみらい地区で開かれた花火大会では、以下のような協力体制が取られていました。
あらかじめ付近で警戒にあたっていた巡視船(横浜海上保安部)などが駆けつけたが、炎上した台船では引火した花火が暴発しており、海上保安部は消火活動は危険と判断し、放水は行わなかった。
炎上した2隻のうちの1隻には5人の作業員が乗っていたが、いずれも海に飛び込んで、駆けつけた消防の船に救助された。
花火の暴発はこのあとも続いたことから、巡視船や消防の船などは夜が明けるまで警戒にあたり、暴発が収まっていることを確認して放水を行った。
横浜海上保安部や警察などが花火大会の関係者のもと実況見分を行い、原因を詳しく調べている。
いかがでしたでしょうか。人々を感動させてくれる花火大会。その開催までの道のりは長く、多くの関係者の努力があることが分かりますね。
主催者の方々に感謝をし、私も花火大会を楽しみたいと思います。
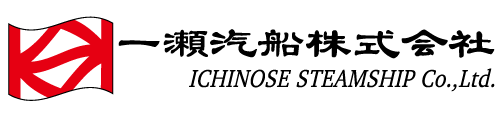
弊社は、「社会を支える船にもっと安全を 海と船の未来をもっと豊かに」を企業理念に、海上運送に関する安全管理支援や、海上運送法上の安全管理規程に基づく内部監査の実施支援をしております。お問合せは、こちらから

